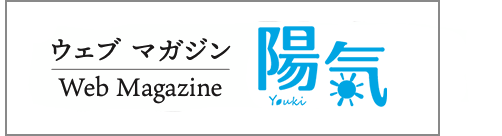9月18日~28日南右2棟で「いのちのいさい」展と題した個展が開催される。
「元の理」に関連して、30枚に及ぶ日本画の連作及び大作が展示される。
「親神様は泥海中から人間を造られた。それは愛と苦心 命の委細の物語」
ポスターには、そんな一行がかかれている。
この個展を開くのは日本画家村田和香さん。教会長夫人でもある。教会では、里親もやりつつ、絵画教室を主宰。さらには、カルチャースクールでの絵画指導をしている。
7月。教会にお邪魔して、出展予定の連作を拝見しつつ、お話をうかがった。
村田さんは京都出身。嵯峨美術短期大学で日本画を専攻した。
日本画との出会いは、高校3年の時、美術大学に行こうと考えていた頃だという。
大学時代は絵に没頭した。それには訳があった。親友との関係が壊れ、人間不信に陥っていたからだという、人と会う事が怖くなった。絵に向かうことでギリギリの均衡を保っていたのかも知れない。

【恩師との出会い】
絵の上達ぶりは周りも認めるほどになっていた。そんなある日、日ごろは来ない老教授が教室に来た。みんな褒められている。期待して待っていた。
絵の前に立った教授の顔は、それまでと一変して、険しい顔になったという。
「写生画帳を見せてごらん、どうして、これが本画になるとこれになりますか」
いきなり完成間近の本画の上に白いチョークで書き直し始めた。更に、床にまでチョークで描き続けられる。何が悪いのか分からなかった。
それが猪原大華先生との出会いだった。
しばらくは、筆が持てなくなった。何が悪いのか、他の先生には指摘されないのに・・・
半年が過ぎた頃、学費の面倒を見てくれていた十二才年上の兄に子供ができた。
その子を描いた。
それを日本画の新人展に公募した。審査員は猪原先生だった。絵は入選した。
「少しよくなりましたね。絵描きにとって少しよくなるというのは、ものすごくよくなったことだから、がんばりなさい」
卒業作品の時もそうだった。卒業作品は180cmx90cmの大作だった。
日本画は、顔料(岩とか貝の粉)を膠(にかわ)で溶いて定着させる。
塗り重ねすぎると、紙が裂けてしまう。極力無駄を省き、膠の濃さを計算をしながら何度も塗り重ねて描いていくという。
それゆえに、本画と同じ大きさの下絵を描いて、主題となる造形を鉛筆で描き、それを赤のボールペンでなぞって本画に写す。
しかし猪原先生は、本画を良しとしなかった。
「下絵の方が良いですね」
鉛筆と赤い線だけの下絵が良い?
締め切りまで1週間
一から描きなおした。
猪原先生の示す道筋を追って、日本画専攻科研究科に残った。
専攻科の卒業作品は、大学で初めての買い上げ作品となった。
卒業後、修養科に行くことが、教会長である母との約束だった。
修養科の後、大学に助手として勤務した。

【挫折】
恩師猪原先生は、いつも思いがけない視点から指摘をしてくださった。
この道を求めて行けばよいのだ……と、思っていた。
勤務して1年目、その猪原先生が他界された。大きな指標を失うことになった。
他の師につくことを薦められたが、その気にはなれなかったという。
独り努力を重ねたが、だんだん道が見えなくなっていった。
村田さんには、高校時代からの彼がいた。唯一気の許せる人だった。
結婚をするつもりでいたし、事実縁談は進んだ。小学校の教員になるという、彼についていくことは、日本画の世界から離れるということも漠然と意識した。
「結婚をするなら、嫁入り道具として講習にいきなさい」
母親とは、そんな約束もあった。
ところが、どこか歯車が狂いだした。目前に迫った縁談は、破談になった。
引き裂かれるような別れに絶望した。
『神様なんていない』そんな思いも頭をよぎった。
それでも、母親との約束をまもり講習に行ったのだという。

【無理、無理、無理】
縁とは不思議なもの。
その講習で出会ったのが、現在の所沢市分教会長であるご主人だったという。
どこに惹かれたのかを私はあえて聞かなかった。
が、きっと「ふわっと包んでくれるような」人柄に惹かれたのかな、と想像している。
縁談は進んで、言葉も文化も違う埼玉は所沢の教会に嫁ぐことになった。
半分流されるように、なりゆきに任せたところもあった。天理教になろうとしていたわけではない、ましてや教会の奥さんなんて想像もしてなかったという。
けれども、教会は教会の若奥さんを迎えたのだ。このギャップは想像を絶するほど大きかったに違いない。
「無理、無理、無理」
別れよう、そんな思いを持っていたときだったという。
少年会本部から、絵本「おやさま」の作画依頼が来た。外国語版の絵本だった。おぢばの御用だったので、絵は詰所で描くことになった。
お腹には長女をお授けいただいていた。
そこから10年、5人の子どもをお与えいただいて、子育ての間は一度も絵筆をもつこともなかった。
「忙しくて……、まったく上を見ることもなく、下を見て暮らしていたかな」
思い返すように、村田さんは話してくれた。

【転機】
そんな頃だった、グループ台(女性ようぼくの美術家のグループ)の諸井松のさんから電話がかかってきた。「一緒にやりませんか?」
嬉しかった。神様は見ていてくださった。神殿で、熱い涙がほほを伝った。
ブランクの後、出品したグループ展でのことだった。
学生の頃からお世話になっていた、深谷忠夫先生と諸井松の先生が、
「まだ、こどもも小さいし、無理では?」
「いや、今描かなかったら、生涯描けなくなる」
目の前で言い合っていたという。
とにもかくにも、絵を描くことになった。
子供のおむつを洗濯をしていた一畳半の場所に、主人が板を置いてくれた。
そこがアトリエになった。
が、絵を描く時間はそうは取れなかった。
そんな時、婦人会本部から「みちのだい」の表紙を描く御用をいただいた。
おぢばの御用なのだから、と、教会での用務の一つが絵を描くことになった。
それでも、5人の子育てが終わったわけではない。経済のこともある。一度は回転ずしのアルバイトに応募したことも。
しかし、自分にできることを思い直し、絵画教室を開くことにした。
これまで、少年会の活動を目的に近所の子供たちを集めて児童画は教えていた。
今度は本格的に日本画を教えてみよう。画力を取り戻す作業から始めなければならない。無料のギャラリースペースをみつけて、そこで個展を開くことから始めた。

【紙芝居おやさま】
思えば、おぢばの御用でつなぎとめてくださったのかもしれない。
おやさまのことをお伝えしたい。
おやさまのお話を紙芝居にして、人様にお伝えしよう。
修養科に入って以来、漠然と思い続けてきたことだった。
けれども、難しくて描けなかった。
義姉が出直した時だった。その兄にもガンの再発。
なんとか助けていただきたい。教祖伝・逸話篇を紐解いては、心に浮かぶおやさまのお姿、お顔を描いていった。
三年後、作品が出来たとき、病床の兄は「お前をリヤカーにのせて日本中をまわりたい」と言って出直したという。
それからは、依頼をもらっては紙芝居を実演する活動を続けている。

【元の理】
会長が教会を継いだ時のことだった。
友人の15歳の娘さんを預かることになった。娘さんは精神を病んでいた。暴れまわる娘さんの世話で追い回された。学校からは、他人の子どもを世話する余裕があるなら、自分の娘を見なさい、と言われたことも。我が子も問題を抱えていた。
夜、その子が眠りについてからおさづけを取り次ぐことにした。
「最初は、憎たらしくてね…」
でも、暗い中でおさづけを取り次いでいる時、
「本当にその子がなんてかわいそうと思えて、熱いおもいがこみ上げたんですよ」
そう思った時だった。
「あったかい」
その子が一言つぶやいた。
「苦しんだり悩んだりしている人の心は泥沼なんじゃないか」
「親神様は、この泥海の中から、愛情をもって、苦心して、人間をつくってくださったのだ」
おやさまのお心が胸に沁みた。
「元の理」を描いてみよう。それが動機だった。
以来、何年も温めてきた。
切っ掛けになった作品がある。
自らの心の中のことを描いた。
「泥海」
春の日展で初めて入選した。
新型コロナ感染症の影響で、自宅待機がふえた。
それが、作品に向かう時間を取ることにつながった。作品は30枚の連作になった。

教会にお邪魔した日に、私たちはこの連作を撮影させてもらった。
撮影は、元プロカメラマンの教会長和泉さん。十分な機材を用意することは適わなかったが、和泉さんが出来る限りのことをしてくださった。
光を当てる角度を変えると、絵は驚くべき表情を見せ始めた。それまで潜んでいたのかと思うほど、見えていなかった色彩や、泥海の中に描かれた造形が飛び込んでくる。
よく見ると、絵はただの平面ではなくて、画材が盛り上がったところもある。塗り重ねた層に光が当たると、絵の表情が変わっていくのだ。



最後に、アトリエを見せてもらった。現在のアトリエで移動すること8か所目なのだそうだ。広い部屋だが、それでもスペース確保のために押入れで寝ているとか。
そこに画材となる顔料の瓶がいくつもならぶ。
日本画の画材は、ただの絵具とは違う。先にも書いたが、岩とか貝のつぶつぶは、本来定着はしない。それを膠でコーティングすることで定着させるのだという。
しかし、それを斑(まだら)なく塗ることが難しいのだという。
何層にも塗られて作品が作られている。その一層一層、一筆一筆に、
「元の理」を通して「親神様の愛と苦心」を感じ取り、おやさまのお心を辿った村田さんの思いも塗り重ねられている。
是非、この「いのちのいさい」展に足を運んで、それを目にしていただきたいと思う。